はじめに|「夫が育児しない」はやる気の問題ではない

「なんで夫は育児をしないの?」
「言わないと動かないのが本当にストレス」そんな悩みを抱える妻は多いです。
でも結論からいうと、夫が育児に参加しないのは“やる気がないから”とは限りません。
実はその裏側には、
- やり方が分からない
- 怒られるのが怖い
- 失敗した経験がある
- 自分の役割は別にあると思っている
といった心理や環境が関わっていることがほとんどです。
この記事では、夫が育児をしない理由 → 妻が知っておくべき心理 → うまく動いてもらう伝え方までを、わかりやすく解説します。
夫が育児に参加しない主な理由

① 育児のやり方が分からず、自信がない
妻は妊娠中から赤ちゃんと生活し、少しずつ“母”になる準備をしています。
しかし夫は、出産後にいきなりスタートラインに立たされるため、抱っこ・沐浴・ミルクなど基本的なことすら「正解がわからない」状態です。
さらに、過去に
- 抱っこすると泣かれた
- ミルクの温度が違うと言われた
などの経験があると、やらないほうがマシと考えてしまいます。
② 手伝ったのに否定された経験がある
妻が忙しいタイミングで「俺がやるよ」と思って動いたのに、
「違う、そうじゃない」「私がやるからいい!」と言われた経験がある夫は多いです。
その結果、「どうせまた怒られる」「自分がやるより、妻に任せた方がいい」
と学習してしまい、徐々に育児から距離を取ります。
③ 役割意識と現実とのギャップで止まってしまう
最近は共働き家庭が増え、「夫=稼ぐ人」「妻=家事育児」といった価値観は以前より弱くなっています。
それでも、
- 自分の父親像
- 会社の雰囲気(残業・帰りづらさ)
- 「自分は家族を養わなきゃ」という責任感
などにより、無意識のうちに“まずは仕事が優先”と考えてしまう男性も多いのです。
つまり価値観としては変わってきているものの、習慣・会社・プレッシャーなどの現実が、夫の行動を止めているケースがよくあります。
④ 男性脳はマルチタスクに弱い
一般的に、男性は「シングルタスク型」、女性は「マルチタスク型」の脳の傾向があるとあります。これは脳科学・心理学の研究でも指摘されており、男女の優劣ではなく「特性の違い」です。
そのため夫は、以下のようなことが同時に起こると処理されず、考える前にフリーズしてしまうことが起こります。
- 赤ちゃんが泣いている
- 洗濯や夕食など、家事の段取りを考えなければいけない
- 妻から「ちょっと付き合って!」「オムツ替えて!」と声が飛んでくる
妻から見ると、「夫が育児しない」「何も出来ない」「なんでソファで固まっているの?」と感じます。しかし、夫の頭の中では次のような思考がぐるぐる回っていることも多いです。
「どれからやればいいんだ…?」
「抱っこしても泣き止まらなかったら怒られるかも」
「正解がわからないから、とりあえず動かないほうが安全かも…」
つまり、行動しないのは「やる気がない」のではなく、「情報が多すぎて脳が処理できていない」「失敗して否定されるのが怖い」という心理状態になっていることが背景にあります。
妻が知っておくべき「言い方の工夫」
| ❌ NGな言葉 | ✅ OKな伝え方 |
| 「なんで私ばっかりなの?」 | 「〇〇してもらえると助かる!」 |
| 「もういい、私がやる」 | 「これ一緒にやってみない?」 |
| 「父親でしょ、やってよ!」 | 「あなたが抱っこすると落ち着くみたい」 |
✔ 感情をぶつけると夫は防御モードになります。
✔ 具体的・短く・否定せず伝えるだけで、夫の反応はガラッと変わります。
「具体的に・短く」お願いする
「育児して」「もっと付き合って」だけでは、夫は何を・いつ・どれくらいならいいのか判断できず、結果として動きません。
夫に育児を頼むときは、内容と時間を具体的に伝えることが大切です。
▼良い具体例
- 「今、オムツを替えるから、新しいオムツ取ってきてくれる?」
- 「あと5分だけ抱っこしてくれると助かる!」
- 「乳瓶を洗って消毒までお願いしてもいいですか?」
このようにすると、夫は「何をすればいいのか」「どれくらいで終わるのか」が明確になり、育児に参加しやすくなります。
成功体験を増やす
夫が育児をしてくれたとき、すぐに感謝や肯定の言葉を返すことが大事です。否定されると「どうせ俺がやっても怒られる」と学んでしまい、育児から離れてしまいます。
▼具体例
- 「ありがとう!助かったよ」
- 「その抱っこ、赤ちゃん落ち着いてるね!」
- 「ミルク作ってくれて助かった、ゆっくり飲めたよ」
というポジティブな声かけで、
**「やる→喜ばれる→またやる→自信が生まれる」** という成功体験のサイクルができ、夫にも育児参加率が一気に上がります。
役割を任せる
「少し手伝って」ではなく、育児の中で1つのことを任せると責任感と担当性が生まれます。
毎回お願いするのではなく、「ここはパパの担当」が決めるのがポイントです。
▼任せると効果的な「パパ担当」例
- 「お風呂上がりの保湿と交換はパパにお願いしたい」
- 「寝る前の絵本と歯磨き担当、担当してくれる?」
- 「離乳食後の片付けはパパに任せていいですか?」
担当制にすることで夫は、「手伝う人」から「一緒に育児をする当事者」に変わります。
まとめ
- 夫が育児をしないのは怠けではなく「怖い・わからない・失敗したくない」心理が原因。
- 最近は共働きが当たり前になった一方で、職場や無意識の価値観がまだ夫の行動を縛っていることも多い。
- 感情で責めるよりも、具体的にお願い→成功体験→ありがとうの循環を作ることが、夫育児の第一歩です。
【当サイトの運営について】
当サイトでは、商品紹介の際にアフィリエイトプログラムを利用しており、リンクを経由して購入された場合、運営者に報酬が発生することがあります。ただし、内容はステマではなく、実体験と正直な感想に基づいて作成しています。

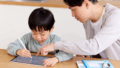
コメント